大丈夫?と訊かれると、反射的に応じてしまう。
大丈夫です、と答えてから、自分の気持ちに気づく。
自分が言う場面を思い出すとわかるけれど、
この言葉、多くは言う人が安心するためのもの。
一緒に何かをしていて、気持ちが一つになっているときなら、
弱音を吐けそうな気がするけれど、
そうでない時は、相手の意図の方を感じるのかもしれない。
とっさに自由なことばが浮かんでこない、閉じた問いかけ。
頑張れという言葉は、つらいとよく話題になるけれど、大丈夫?も同じこと。
自分と違うところに立っている人が、一方的に言葉を投げているような、
そんな風に感じられるもの。
だから、ひとことで済ませずに、添える何かが必要なのかもしれないね。
そして、言葉をかけたいと思ったことに目を向けたなら、
その言葉が受け容れづらくても、
声をかけた(かけてくれた)ことの方を、もっと大事にしていきたい。
どうですか? も要注意。
福祉関係の調査中、ポンと出てきたこのことばに、詰まった。
人と違っても、私の日常。それをどう表現したらいいものか。
と思いながら、ふと、前回の調査との相違点を言えばいいと気づいた。
そう、相手の意図がとっさにとれなかった。
この言葉だけ投げるのは、あまりに不親切。もうひとことがあったなら。
主治医に言われるのは慣れたけれど。
子どもの頃思った。
貧しい国に生まれていたら、生きていられなかった。
両親の生活が安定しているから、弱い私でも安心して生きていられる。
それを、裕福と表現できると思う。
お金ではなく、生活する基盤や力がたくさんあるから、裕福、と。
親が患者会にいる子どもも、裕福といえるのではないだろうか。
集まりに参加したり、会報で情報を得たり、会費を払ったり、
子どもの病気のことを思い、行動しているのだから。
もちろん、会に関わらなくても、立派に病児を育てていらっしゃる方はいる。
でも、病気を避けて通りたくて、会が目に入らない方もあるだろうから、
会にいれば確実に裕福なのだと思う。
裕福でないところにいる子どもは、どうしているのだろう。
病気に対応できない親だったら、病院へも行かないのではないか。
両親がいなくて施設にいる子は、きちんと治療が受けられるのか。
ふだん見えないから、なかなか考えることもできないけれど、
日本の中にだって、きっとある。
わかっても手を差し伸べることはできないかもしれない。
けれど、だからこそ、心に留めておきたい。
同じものって、どうしてこんなに気になるのだろう。
同じ病名は目に留まるし、連絡があるとうれしい。
だけど、20代の頃、同病の人から手紙をいただいた時は、素直に応じられなかった。
たいてい修復手術をしていない人だから、状況が同じではないし、
それなのに同じだと思われて、日常どうしているかと問われたら、
どう返答していいものか、わからなかった。
手術受けられた自分の幸運が、重荷になった。
今、同じ手術でも、小さいうちにできるからか、
健康な人とほとんど変わらない生活をしているという方の姿を
よかったね、と素直に感じながら、
ああ、私は考えが狭かったのだと思う。
自分より元気な人の姿は、希望だったかもしれないのだから。
同じだからと考えるとき、
直線上のこの辺とあの辺というように見えるから、違いが際立ってくるけれど、
自分と相手の違いをきちんと認められるといいのだろう。
多分、今ならそれができるようになったのだと思う。
彼らがいるときにできなかったことは、とても残念。
下の文を改めて読んで思い出した。
身体の動きがおぼつかなくなった高齢の方に、
転ばぬ先にと杖を持つことを勧めているという話がある。
骨折して動けなくなったら困るから、予防のために。
生きる時の動きがおぼつかない、病気や不安を抱える人も、
転ばぬ先の杖を求めているのかもしれない。
その人にとって合う杖があるといいんだね。
それは、これをしていれば幸せという、生きがいだったり、
大事なものであったりするのかもしれない。
杖みたいにわかりやすいものではないのだけれど、
それぞれが、自分にあった杖を持てたらいいんだね。
慢性疾患の心理ケアの本は、糖尿病、腎臓病が多くて、その他はあまりない。
心臓リハビリでは、虚血性心疾患が主な対象のようで、ピンとこない。
それだけ、先天性心疾患の大変さは、わかりづらいとも言える。
なぜ考えられてこなかったのか、不思議に思っていたけれど、
糖尿病や腎臓病は、治療の必要性が高いものだから、
それだけ医療者の側もきちんと考えなければならなかったからと思う。
子どもの頃からインスリンの注射がなければ生きていかれないⅠ型糖尿病は、
自分で注射し、血糖がコントロールできるように、指導される。
透析の必要な腎臓病でも、それをしなければ生きていかれないから、
時に反発しつつ、受け入れて、自分の時間の多くを通院に割く。
その治療は過酷でもあるけれど、それだからしっかりと意識しやすいし、
だから反発することもできて、そのことが理解されやすいと思う。
私に薬が必要なかった頃、Ⅰ型糖尿病の人から病気のことを聞き、
注射の入ったポーチを見ながら、頼るものがあることをうらやましく感じた。
年一度の検診で医師に会うだけでは、心もとないものだったから。
病気があって、本当にこれで困るというわけではないけれど、
些細なあれやこれがあって、支えになるものを求めていたから。
今飲んでいる薬も、なければ即生きていかれないというものでもなく、
薬が身体に合い、悪いことがなければいい、くらいなあいまいさがつきまとう。
予後も、標準的なコースはないように感じる、というか、
ある時点で次に起きるかもしれないことを、予測できたとしても、
他の病気より多岐にわたり、こうなると言えないように感じる。
そんなあいまいさの中で、不安に思い、迷い、悩むのだと思う。
もしかしたら、病気や障害に対して手を貸したいという相手も先生も、
そのあいまいさから、関わるきっかけがみつからないのかもしれない。
「癒されて生きる」(岩波現代文庫)を読んだ。
柳澤桂子さんが病気で得たものを、科学者の視点をこめて描いている。
かかった病気は長く原因が特定できずに、的確な治療を得られず、
診断ができなかったゆえに、つらい症状があっても病いと認めてもらえなかった。
激しい症状のために研究者の職を断念、家族としての役割も全うできない、
そんな過酷な状況も、客観的な短い文章で静かに綴られている。
私の病気の経験や思いと重なるところもあった。
中で、神秘体験に目が留まった。
高揚感と、大きなものに包まれた感覚。起きたことの全貌を表現できない、不思議な経験。
精神科医の神谷美恵子によれば、深い苦悩でどんづまりまで行った人に起き、
価値体系の変換をもたらし、生命そのものからの湧き出るよろこびだという。
柳澤さんも、大切にしていた職を辞めざるを得なくなった時に起きたそうだ。
ごく当たり前に、ああ、そういうことはあるだろうと了解できたのは、
表現のできない、身体で感じたとしかいいようのない深い経験が私にもあるから。
私のはパニック発作*で、そこから感じ取ったものは全く違うものだし、
そのときに価値観の変換は起きていないけれど、
もしかしたら、エネルギーの働く向きが違うだけかもしれない、と感じた。
(*:診断基準とは微妙に違うとも思いながら、
メインで感じたものは理解不能の突然の恐怖だったので、パニックとしておく)
柳澤さんも神谷さんも、社会的役割を自身の努力で築いていた人、
その意味では、生きている基盤が私とは違うように思う。
病気に対する周囲の気遣いは、当たり前に社会にいることを拒む面もあったし、
どこかでそれでもいいんだと思う自分がいた。
身体を守ることを優先すれば、一生懸命やったつもりでもどこか満足できない。
仲間を失う中では、何故自分が生きていられるのかと、自身の生を時に疑う。
社会的な面でも心理的な部分でも自分の位置取りを掴むことが難しかった私。
何故かはわからない、苦手な場面の中でさらに逃げ道を失ったときに起きたパニックは、
身体が十数センチほど後ろに飛ばされたような衝撃と、強い恐怖感。
それでも壊れずにそこにいる、そして、確かに自分に核(中心)があると感じられた経験は、
自分がここで生きるつよさを持っていることを確認できたと同時に、
自身の基点を得る足がかりになったように思う。
それは、柳澤さんたちが社会的役割から降りなければならなかった時、
それより大きなものを感じたのとはちょうど逆の向きではないだろうか。
人の中にあるエネルギーの激しさ、心の不思議さ。
ふとした時に恐怖感が蘇ることも、歳月の流れの中で減っていき、
苦手な場面で問題はあっても、回避の方法もいくらか覚え、
さまざまな洞察を得られて、賢くもなった。
苦しみも、恐怖も、感じないで済むほうがいいと思われるけれど、
安易に癒されていたならば感じることのできなかった深い大事な経験とみれば、
つらさや苦悩の中にいた長い時間を、ひとりで向き合っていられたことは、
何にも代えがたい、恵まれたものだったのかもしれない。
病気の人が日常暮らしていく上のヒントになるものは少ないけれど。
最近は病気や障害に関して、看護や福祉といった職業上の支援者のためだけでなく、
もっと広い視点からまとめられた本もいくつか出てきた。
・病気だけど病気ではない -糖尿病とともに生きる生活世界 (浮ヶ谷幸代 著/誠信書房)
・透析者のくらしと医療 (日本評論社)
・障害・病いと「ふつう」のはざまで-軽度障害者どっちつかずのジレンマを語る(田垣正晋 編/明石書店)
病気や障害のある人はどういう状況におかれているか、何が必要なのか、
当事者の言葉も大事だけれど、それでは狭いところに留まってしまうから、
きちんとまとめて検証することも必要。
それが研究なのだけど、研究書は読みづらいし、すぐに役に立たないから、
もう少し、当事者の力になるものはできないのかしら。
自分の病気に関する論文を見ると、どこか違うと感じることが多い。
病気の部分に焦点を当て、様々な人の経験をならしてこうである、と言わなくてはいけない、
研究とはそういうものだから、
いろいろな背景を持ってそこにいる個人にとってみたら、違うというのも、ある意味当然。
まして、健康な人だったり、職業的な支援者だったり、たいていは立場の違う人がしているし、
当事者だったとしても、様々なことすべてに応えられなくて、泣く泣く落とすものもあるから、
ある事柄に対して、勘違いの解釈も、大事なポイントの見落としもあるかもしれない。
だから研究は役に立たない、というのではなくて、どこが違うのか、どうしたらいいのか、
それを言っていかれたら、役立つものになるのだよね。
しっかりみて、伝えていかれたらいいのだけれど。
それをするには、もう一つ身体がほしくなる。
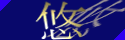 メニューへ⇒
メニューへ⇒